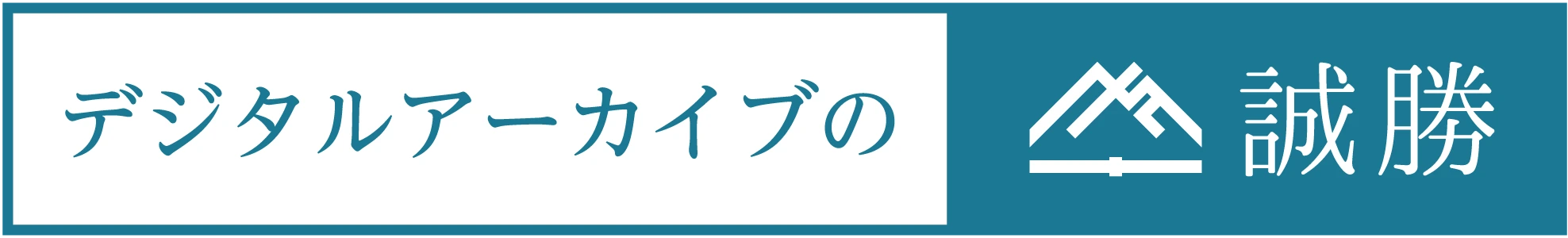デジタルアーキビストという職業をご存知でしょうか。
図書館司書や博物館学芸員と比べるとまだまだ認知度が低いかもしれませんが、急速なデジタル技術の発達やインフラの普及にともないデジタルアーカイブというものの重要性が高まっている現在、徐々に注目があつまっている職業です。
今回はデジタルアーキビストの仕事の内容や、その活躍の場について詳しくご紹介します。
【お見積り無料】プロのデジタルアーキビストが担当!企業向けアーカイブ構築サービスはこちら
アーカイブとデジタルアーカイブって何?
デジタルアーキビストとは、一言でいえば文化資源であるデジタルアーカイブを記録・保存・管理するプロフェッショナルのことです。まずはデジタルアーキビストが扱うことになる、アーカイブやデジタルアーカイブについて簡単にご説明します。
「アーカイブ」の意味
そもそもアーカイブって何だろうと思う人は多いでしょう。聞いたことはあるけど、いまいち意味がわからないのが「アーカイブ」という言葉ではないでしょうか。
アーカイブ、または複数形のアーカイブズという言葉が使われていますが、古文書や公文書、記録文書の集合、もしくはそうした文書を保管する場所、というのが本来の意味です。言い換えると、貴重で文化的な価値があり、保存すべき資料はすべてアーカイブであり、また公文書館のような保存機関もアーカイブと呼ばれる場合があります。
「デジタルアーカイブ」の意味
次にデジタルアーカイブについて説明します。
「アーカイブ」に「デジタル」をつけた「デジタルアーカイブ」は、実は日本で生まれた和製英語です。1996年に日本で設立された「デジタルアーカイブ推進協議会(JDAA)」の準備会議の中で、当時東京大学教授であった月尾嘉男氏が初めて提案したものだとされています。
古文書や公文書、記録文書といったアーカイブをデジタル化したものがデジタルアーカイブですが、それだけにとどまらず、出版物、文化財、その他歴史資料等、有形・無形を問わずあらゆる知的資産を対象としている点が特徴です。デジタル情報の形で知的資産を記録し、その情報をデータベース化して管理、さらにネットワーク技術を用いて広く公開し活用することが、デジタルアーカイブの役割です。
デジタル化されていないアーカイブは現物資料であるため、保管している機関でしか目にすることができません。それに、貴重な資料や古くてぜい弱な資料はいつでも公開されているわけではありません。しかしデジタルアーカイブであれば、いつでも、どこでも、誰でも自由にその情報を見たり、活用したり、研究したりすることができます。これがアーカイブをデジタル化することの一番のメリットと言えるでしょう。
用途や媒体に応じてデータの形式を使い分けることも簡単になり、情報の発信や共有という点でも大きなメリットがあります。
アーカイブとして保存されている文化財や文化資産、たとえば古文書などの紙資料、写真や映像を記録したフィルムなどは、経年によって劣化が進行していくことが避けられませんが、一度デジタル化してしまえば、文字も画像も映像も音声も劣化することがありません。アーカイブを未来に遺すための手段としてもデジタルアーカイブは重要な役割を果たしているのです。
なお、デジタルアーカイブについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
デジタルアーキビストとは
それでは次にデジタルアーキビストの仕事の内容を解説します。
- 資料の文化的価値の理解
- デジタル化の技術
- 法的理解と倫理
ひとつずつ具体的に説明しましょう。
1. 資料の文化的価値の理解
最初に説明した通り、アーカイブとは貴重で文化的な価値があり、保存すべき資料のことです。デジタル化にあたっては、その資料の価値を正しく認識するための、幅広い知識と専門分野の深い知識がデジタルアーキビストには必要とされます。さらに言えば、そのアーカイブを公開することにどんな意味があるのか、それがどんな文化活動につながるのか、といった視野も求められます。
2. デジタル化の技術
デジタルアーキビストには、有形・無形の貴重な資料をデジタル化し、デジタルアーカイブを作成する能力が当然ながら必要となります。どのような機材(デジタルカメラ、スキャナなど)を使うのか、そしてどのようなシステムでデータベース化していくのかを適切に判断する能力ですね。
デジタル技術は日々急速に進歩しています。ですから、そうした技術に関する新しい情報を積極的に学び続ける意欲が大事になります。
3. 法的理解と倫理
デジタルアーカイブを作成すると言っても、何でもかんでもすべてデジタル化して公開すればいいわけではありません。
デジタル化の対象となる有形・無形の文化資産には、複製する権利、上演する権利、展示する権利などを含む著作権(知的財産権)があります。その他にも個人情報保護法に基づき、著作者のプライバシーに配慮する必要もあります。インターネットやマルチメディアの普及にともない、現行の著作権法ではカバーできない事例が増えてきています。そうした課題に対し、デジタルアーカイブ整備推進法(仮称)の制定が進んでいます。著作権法も改正されていくでしょうから、情報を常にアップデートしていく必要があります。
デジタルアーキビストには、こうした流動的な法の理解と倫理観念を踏まえた上でデジタルアーカイブを作成・公開することが求められるのです。
なかなか高度な専門職だということが想像できますよね。